2021年4月28日に発表されたある研究レビューは、怪我や旅行など、トレーニング量を減らさざるを得ない状況において、これまでに培った運動効果を失わずに済む「最低限のトレーニング量」について深く掘り下げたものです。米国陸軍環境医学研究所の研究チームが実施したこのレビューは、既存の体力および筋力を維持するために必要な最小限のトレーニング量に関する貴重な洞察を提供しています。
このレビューは、過去の「トレーニング量」に関する包括的なデータを統合し、以下の3つの主要な要素に焦点を当てて分析を行いました。
- 頻度: 週に何回トレーニングを実施すべきか。
- 量: 持久力トレーニングの継続時間、またはセット数やレップ数。
- 強度: どれだけ高い負荷でトレーニングを行うべきか。
これらの分析から導き出された重要な結論について、以下に詳細を述べます。
持久力の維持:
まず、心肺機能および持久力を維持するために必要なトレーニング量について考察します。この分野に関する議論は、主に1980年代初頭に実施されたデータに基づいています。
具体的には、最大心拍数の90〜100%に達する強度で40分間のサイクリングを週6日、10週間にわたって実施した結果、心肺機能の指標であるVO2maxが20〜25%向上しました。その後、トレーニング頻度を週2〜4日に減らしたにもかかわらず、15週間にわたりこの向上したVO2maxが維持されたことが報告されています。これらのデータに基づき、研究者らはトレーニングの総量と強度を維持する限り、週に2回のセッションでも持久力の維持には十分であると結論付けています。週に2回のトレーニングで持久力が維持できるという事実は、多くの人々にとって喜ばしい知見と言えるでしょう。
ただし、注意すべき点として、VO2maxの維持と長時間の競技における持久力の維持は同一ではないと指摘されています。これは、週2回のトレーニングがVO2maxを維持する一方で、マラソンといった特定の長距離競技のパフォーマンス向上には直接的に寄与しない可能性を示唆しています。
また、上記のテストでは「1回あたりのトレーニング時間」と「強度」も詳細に検証されており、以下の結論が導き出されています。
- 1回あたりのトレーニング時間をベースラインの3分の1(13分)または3分の2(26分)に短縮した場合でも、15週間にわたってVO2maxの向上が維持されました。
- しかし、短時間持久力は両グループで維持されたものの、トレーニング時間を13分に短縮したグループでは、2時間のランニングテストにおける成績が低下しました。
- トレーニング強度を3分の1に低下させた場合(最大心拍数の90〜100%から82〜87%に低下)、VO2maxおよび長時間の持久力が低下しました。さらに、強度を3分の2に低下させた場合(61〜67%に低下)には、トレーニングによって得られたメリットのほとんどが失われる結果となりました。
これらの知見から、トレーニングの頻度やセッション時間は短縮可能であるものの、負荷(強度)の維持が心肺機能の維持に不可欠であることが示唆されます。時間的効率性は得られるものの、トレーニングの質に対する精神的な要求は依然として高いと言えるでしょう。
筋力の維持:
筋力トレーニングに関する研究は多様なアプローチが存在するため、持久力トレーニングと比較して一概に結論を導き出すことは困難であるとされています。しかしながら、全体的な傾向としては持久力トレーニングと同様のパターンが見られます。すなわち、最も重要な要素は強度(使用する重量)であり、この強度を維持できるのであれば、トレーニングの頻度やセッション時間は短縮しても問題ないと結論付けられています。適切な負荷を維持することで、筋力および筋肉量の両方を数ヶ月間維持することが可能であると報告されています。これは、多忙な時期にジムに通う時間が限られている人々にとって、励みとなる知見です。
より詳細な傾向としては、以下の点が挙げられます。
- 頻度: 複数の研究が、週に1回のトレーニングでも筋力と筋肉量の維持には十分であることを示唆しています。
- 量: トレーニング量に関しても同様に、1エクササイズにつき1セットの実施で筋力と筋肉量の維持に効果的であるという報告が多く見られます。
- 高齢者への配慮: ただし、60歳以上の高齢者の場合、筋肉量の維持には週2回のトレーニングがより効果的であり、各エクササイズで2セット実施することが推奨される傾向にあります。
以上のことから、負荷さえ維持できれば、予想以上にトレーニング量を減らしても問題なく筋力と筋肉量を維持できる可能性が示唆されます。ただし、本レビューが対象としているのは、比較的強度の高いトレーニングを継続的に実施してきたアスリートや個人である点に留意が必要です。そのため、一般的なトレーニーにおいては、これらの結論が必ずしもそのまま当てはまらない可能性も考慮すべきでしょう。
現在の体力と筋肉を維持するための最小限のトレーニング量に関する考察:
2021年4月28日に発表されたある研究レビューは、怪我や旅行など、トレーニング量を減らさざるを得ない状況において、これまでに培った運動効果を失わずに済む「最低限のトレーニング量」について深く掘り下げたものです。米国陸軍環境医学研究所の研究チームが実施したこのレビューは、既存の体力および筋力を維持するために必要な最小限のトレーニング量に関する貴重な洞察を提供しています。
このレビューは、過去の「トレーニング量」に関する包括的なデータを統合し、以下の3つの主要な要素に焦点を当てて分析を行いました。
- 頻度: 週に何回トレーニングを実施すべきか。
- 量: 持久力トレーニングの継続時間、またはセット数やレップ数。
- 強度: どれだけ高い負荷でトレーニングを行うべきか。
これらの分析から導き出された重要な結論について、以下に詳細を述べます。
持久力の維持:
まず、心肺機能および持久力を維持するために必要なトレーニング量について考察します。この分野に関する議論は、主に1980年代初頭に実施されたデータに基づいています。
具体的には、最大心拍数の90〜100%に達する強度で40分間のサイクリングを週6日、10週間にわたって実施した結果、心肺機能の指標であるVO2maxが20〜25%向上しました。その後、トレーニング頻度を週2〜4日に減らしたにもかかわらず、15週間にわたりこの向上したVO2maxが維持されたことが報告されています。これらのデータに基づき、研究者らはトレーニングの総量と強度を維持する限り、週に2回のセッションでも持久力の維持には十分であると結論付けています。週に2回のトレーニングで持久力が維持できるという事実は、多くの人々にとって喜ばしい知見と言えるでしょう。
ただし、注意すべき点として、VO2maxの維持と長時間の競技における持久力の維持は同一ではないと指摘されています。これは、週2回のトレーニングがVO2maxを維持する一方で、マラソンといった特定の長距離競技のパフォーマンス向上には直接的に寄与しない可能性を示唆しています。
また、上記のテストでは「1回あたりのトレーニング時間」と「強度」も詳細に検証されており、以下の結論が導き出されています。
- 1回あたりのトレーニング時間をベースラインの3分の1(13分)または3分の2(26分)に短縮した場合でも、15週間にわたってVO2maxの向上が維持されました。
- しかし、短時間持久力は両グループで維持されたものの、トレーニング時間を13分に短縮したグループでは、2時間のランニングテストにおける成績が低下しました。
- トレーニング強度を3分の1に低下させた場合(最大心拍数の90〜100%から82〜87%に低下)、VO2maxおよび長時間の持久力が低下しました。さらに、強度を3分の2に低下させた場合(61〜67%に低下)には、トレーニングによって得られたメリットのほとんどが失われる結果となりました。
これらの知見から、トレーニングの頻度やセッション時間は短縮可能であるものの、負荷(強度)の維持が心肺機能の維持に不可欠であることが示唆されます。時間的効率性は得られるものの、トレーニングの質に対する精神的な要求は依然として高いと言えるでしょう。
筋力の維持:
筋力トレーニングに関する研究は多様なアプローチが存在するため、持久力トレーニングと比較して一概に結論を導き出すことは困難であるとされています。しかしながら、全体的な傾向としては持久力トレーニングと同様のパターンが見られます。すなわち、最も重要な要素は強度(使用する重量)であり、この強度を維持できるのであれば、トレーニングの頻度やセッション時間は短縮しても問題ないと結論付けられています。適切な負荷を維持することで、筋力および筋肉量の両方を数ヶ月間維持することが可能であると報告されています。これは、多忙な時期にジムに通う時間が限られている人々にとって、励みとなる知見です。
より詳細な傾向としては、以下の点が挙げられます。
- 頻度: 複数の研究が、週に1回のトレーニングでも筋力と筋肉量の維持には十分であることを示唆しています。
- 量: トレーニング量に関しても同様に、1エクササイズにつき1セットの実施で筋力と筋肉量の維持に効果的であるという報告が多く見られます。
- 高齢者への配慮: ただし、60歳以上の高齢者の場合、筋肉量の維持には週2回のトレーニングがより効果的であり、各エクササイズで2セット実施することが推奨される傾向にあります。
以上のことから、負荷さえ維持できれば、予想以上にトレーニング量を減らしても問題なく筋力と筋肉量を維持できる可能性が示唆されます。ただし、本レビューが対象としているのは、比較的強度の高いトレーニングを継続的に実施してきたアスリートや個人である点に留意が必要です。そのため、一般的なトレーニーにおいては、これらの結論が必ずしもそのまま当てはまらない可能性も考慮すべきでしょう。
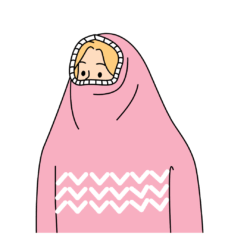


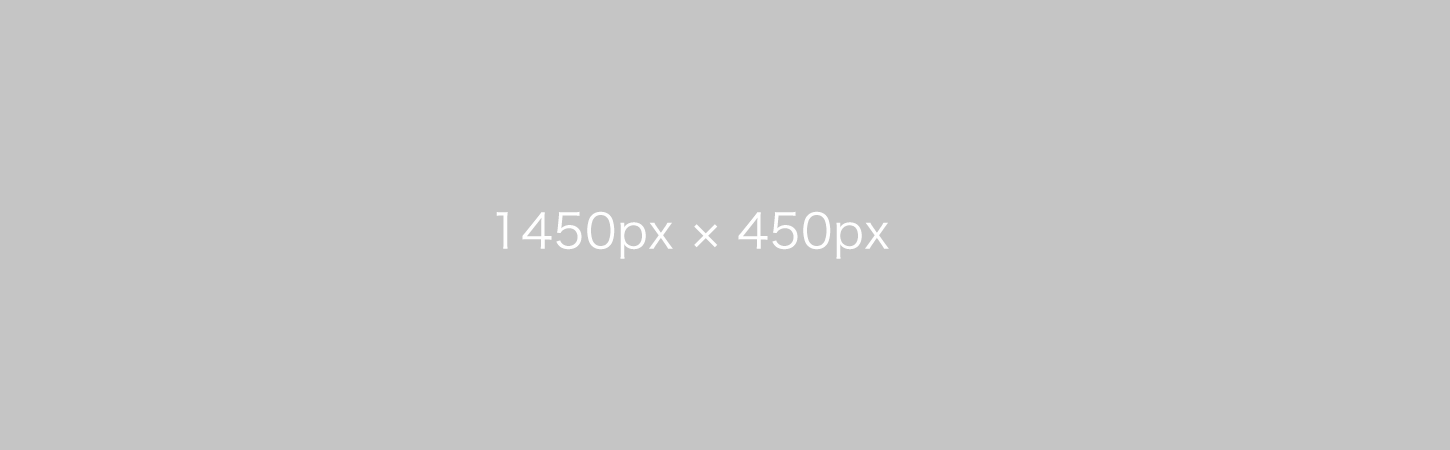







コメント