「自分が乳児だった頃に何を口にしていたか」を正確に覚えている人は、まずいないでしょう。しかし近年の疫学研究は、「人生最初の約1,000日間に摂った栄養が、半世紀以上先の健康状態にまで影響しかねない」と指摘しています。とりわけ砂糖の摂取量が将来の肥満や糖尿病リスクと密接に結びついているという報告が増えており、その代表例として第二次世界大戦直後の英国を対象に行われた大規模コホート研究が注目を集めています。
研究の舞台裏:
1942~1953年の英国では、戦時下の食糧不足を背景に砂糖や脂肪の使用量が国家ぐるみで制限されていました。1945年当時、国民1人あたりの砂糖消費量は現代水準の半分程度。甘いお菓子は贅沢品で、一般家庭の食卓に並ぶ機会はごく稀だったと言われています。
配給制度は1953年を境に終了し、国民の栄養環境は一変しました。
• 砂糖摂取量 +50〜60%(約+25g/日)
• 脂質摂取量 +10〜20%(約+6g/日)
• 総エネルギー +160kcal/日(主に砂糖由来)
栄養状況がこれほど劇的に変わったことで「自然実験」の条件がそろい、研究者たちは配給制度の有無で生まれた時期が異なる人々を比較することで、乳幼児期の栄養と中高年期の健康との因果を探ることにしました。
調査の設計と結果:
調査対象は英国出身の60,183名。出生年によって次の2群に分けられました。
- 配給期間中に誕生(1942〜1953年)
- 配給制度終了後に誕生(1953年以降)
被験者が50~60代となった時点で健康指標を評価したところ、戦時配給期に生まれた人々は以下のように疾病リスクが低いことが判明しました。
• 2型糖尿病 −36%
• 高血圧 −19%
• 肥満 −31%
さらに配給期間が長く続いた生年月日の人ほど保護効果が強いことから、「生後2~3年までの食生活」が長期の代謝プロファイルを方向づける可能性が示唆されました。
鍵となる“最初の1,000日”理論:
栄養学では、受胎から2歳頃までの約1,000日間を「ヒトの健康設計図が描かれる決定的な窓」とみなします。この間に
• 臓器の成長と機能設定
• ホルモンシステムの初期化
• 基礎的なエネルギー代謝パターン
が大きく形づくられるため、過不足いずれの栄養バランスも将来リスクに直結しやすいと考えられています。今回焦点となったのは「過剰な糖質」の影響で、砂糖のわずかな摂取差が数十年後の疾患率にまで尾を引いていたという点は衝撃的です。
解釈と注意点:
もっとも、配給終了後は砂糖だけでなく脂質や総カロリーも増えており、「砂糖だけが悪者」と断定するのは早計です。別の研究では、
• 高カロリーの離乳食が肥満傾向を固定化
• 加工脂肪の過剰摂取がレプチン抵抗性を誘発
• 乳幼児期の蛋白質過多が成長ホルモン分泌を過刺激
といった報告もあります。また、幼少期の味覚経験が生涯の嗜好を左右する可能性も見逃せません。実験動物では、早くから甘味を与えられた個体ほど甘い食品を好むようになり、高脂肪食を与えられた個体は食物依存傾向が強まることが示されています。人間でも幼児期に菓子類へ慣れ親しんだ子どもは成人後も甘味摂取量が多い傾向にあるため、今回のリスク低下は代謝面だけでなく「生涯の食習慣形成」に由来している可能性があります。
実生活への示唆:
現代の日本では、加工食品やスナック菓子が家庭内に常備されるのは珍しくありません。だからこそ「最初の1,000日間」に与える食べ物の質と量は、過去より一層大きな意味を持つといえます。厚生労働省やWHOは、
• 1歳未満の乳児には加糖食品を避ける
• 生後6ヶ月までは母乳を推奨
• 離乳食はできるだけ加工度の低い食材で
といったガイドラインを提示していますが、今回の英国の自然実験はこれらの勧告を裏づける好例と言えるでしょう。
まとめ:
乳幼児期に控えめだった砂糖が、60年以上先の生活習慣病リスクを左右していた──この事実は「幼い頃の食卓が未来の健康資産を決める」というメッセージを強烈に示しています。親世代にとっては、目先の便利さだけでなく、子どもが迎える半世紀後の健康まで視野に入れた食習慣づくりが求められているのかもしれません。
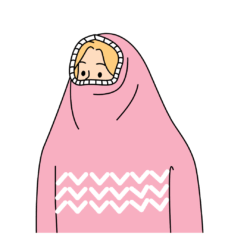


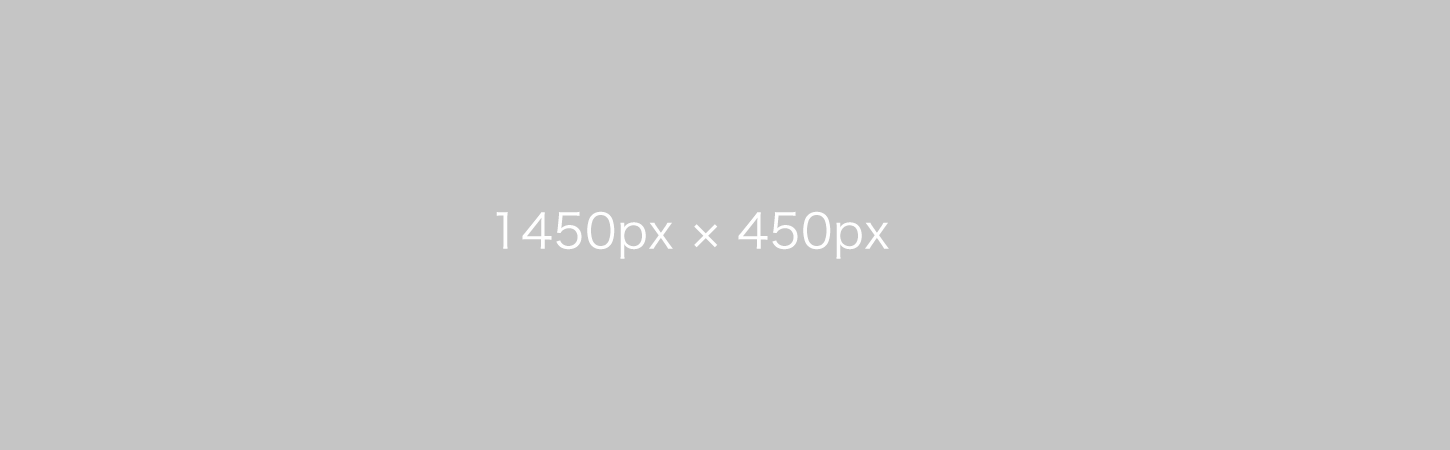
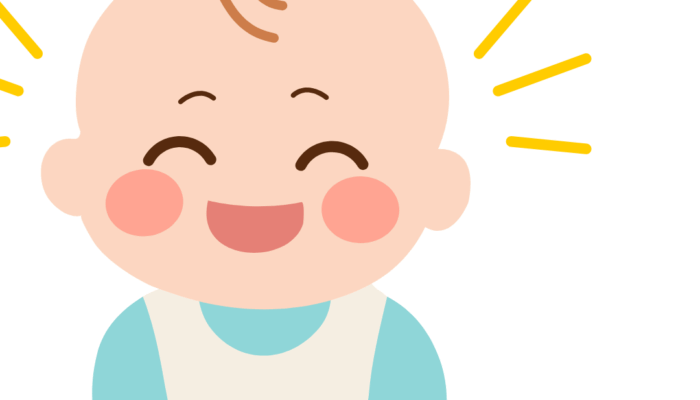



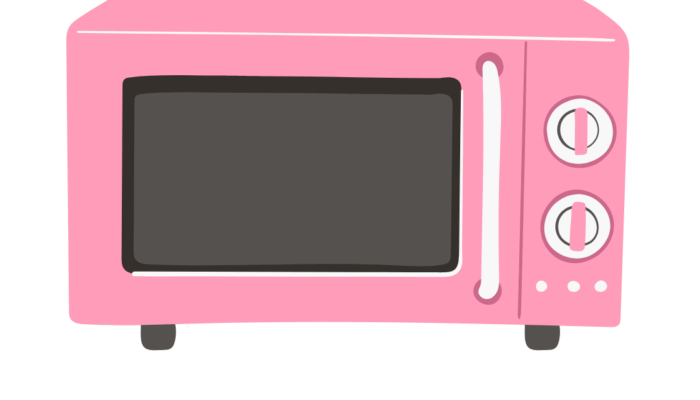


コメント