人間は将来の価値を現在価値に換算する際、**「時間的割引」**を行います。しかし、この割引率が個人の主観によって大きく歪められることが、長期的な資産形成を阻害する要因となっています。
双曲割引の問題
経済学的には一定の割引率で将来価値を計算すべきですが、実際の人間の行動は**「双曲割引」**のパターンを示します。これは、近い将来に対しては高い割引率を適用し、遠い将来に対しては低い割引率を適用する傾向です。
具体例:
- 「明日の1万円」vs「今日の9,500円」→ 今日の9,500円を選ぶ(年利約1,826%の割引率)
- 「1年後の1万円」vs「11ヶ月後の9,500円」→ 1年後の1万円を選ぶ(年利約60%の割引率)
複利効果の過小評価
この時間的割引の歪みにより、多くの人が複利効果を過小評価しています。アインシュタインが「人類最大の発明」と称した複利の力を、正しく理解している人は驚くほど少ないのです。
複利の威力の実例: 月3万円を年利5%で積み立てた場合:
- 10年後: 約452万円約452万円 (元本360万円 + 利益92万円)
- 20年後: 約1,233万円約1,233万円 (元本720万円 + 利益513万円)
- 30年後: 約2,497万円約2,497万円 (元本1,080万円 + 利益1,417万円)
30年間で元本の2.3倍以上に成長し、利益が元本を上回ります。しかし、多くの人はこの「雪だるま式」の成長を直感的に理解できず、短期的な変動に一喜一憂してしまいます。
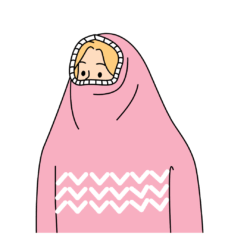


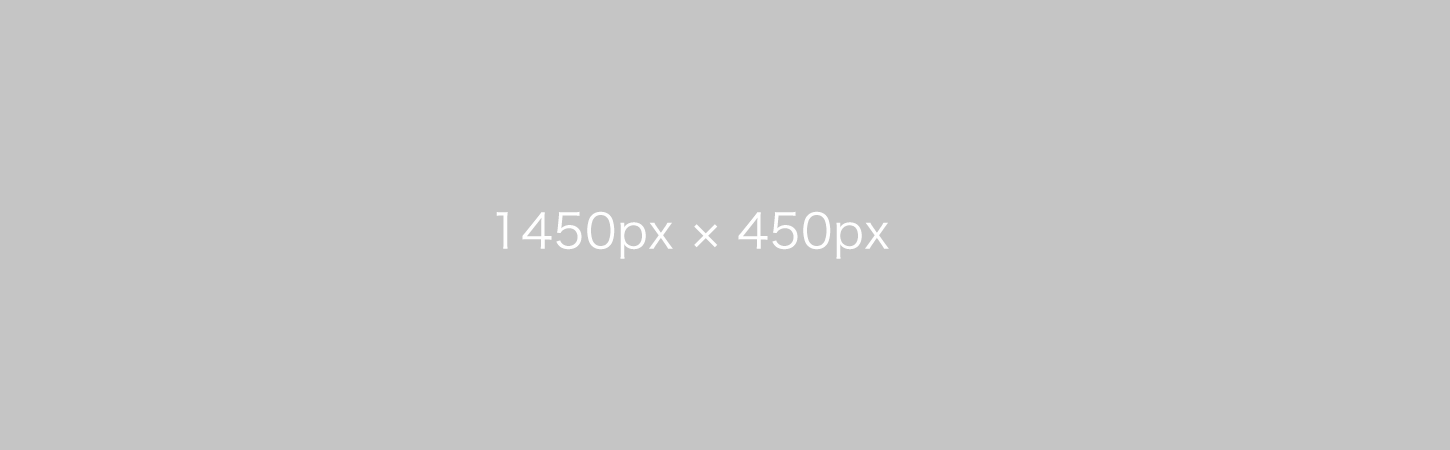
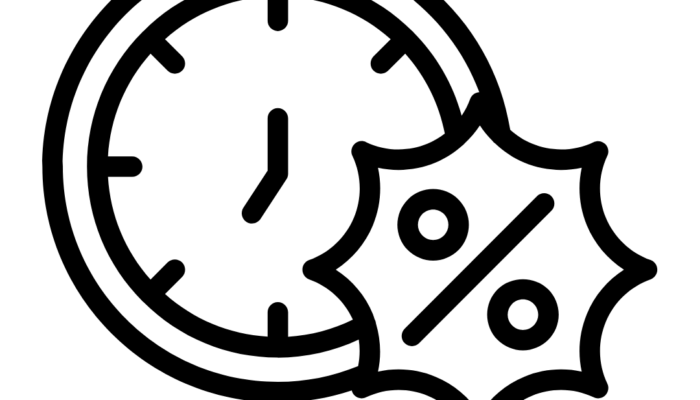



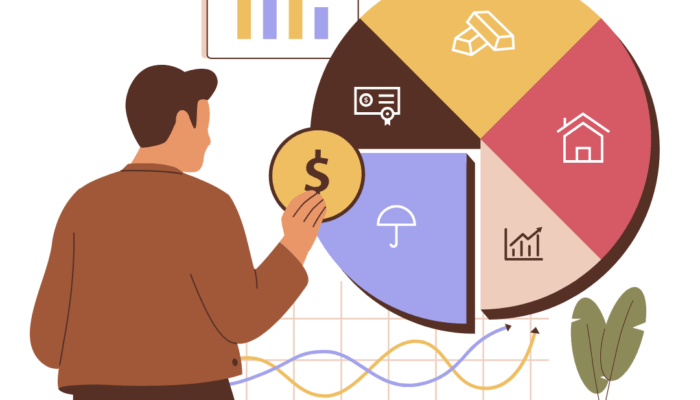


コメント