予測が外れ続ける評論家の真実
世の中には、不思議と予想がことごとく外れてしまう人がいます。彼らが「上がる」と断言した株は下がり、「ヒットする」と予測した商品は鳴かず飛ばず。「逆神」と揶揄されるこうした現象は、評論家やコメンテーターの世界でしばしば耳にします。しかし、果たしてこのような「逆神」は本当に存在するのでしょうか?それとも、単なる偶然の一致に過ぎないのでしょうか?
この長年の疑問に、ある研究チームがオンライン映画レビューのデータを深掘りすることで迫りました。
オンライン映画レビューで検証する「逆神」現象
研究者たちが注目したのは、有名な映画レビューサイト「ロッテン・トマト」に掲載された、公開前の映画評論家によるレビューです。彼らは、評論家が良いと評価した映画が興行的に失敗し、逆に酷評した映画が成功するという、評価と結果が常に逆転するような評論家が本当に存在するのかを調査しました。
ちなみに、これまでの研究では、プロの批評家や一般視聴者の評価が映画の興行収入と一定の相関があることが示されています。肯定的なレビューも否定的なレビューも興行収入と関連性があり、特に否定的なレビューの影響は時間が経つにつれて薄れる傾向にあるとのこと。この事実を踏まえれば、常に評価と結果が逆を行くレビュアーが存在してもおかしくない、という仮説が成り立ちます。
「逆神」レビュアーは実在した!その特徴とは?
大量のレビューと興行成績を詳細に分析した結果、研究チームは驚くべき結論に至りました。なんと、**「逆神」と呼べるレビュアーは確かに存在したのです。**彼らが批判した映画は成功しやすく、絶賛した映画ほど失敗に終わる傾向が確認されました。
さらに興味深いのは、これらの「逆神」レビュアーの文章スタイルに、いくつかの共通する特徴が見られたことです。
- 自己言及代名詞の少なさ: ポジティブな批評を書く際、彼らは「私は」「自分の意見では」といった自己言及的な表現をほとんど使いませんでした。これは、自身の能力を過信し、あたかも客観的な事実を述べているかのように見せようとする心理の表れかもしれません。
- フィラー(つなぎ言葉)の少なさ: 「You know」や「Like」といった無意識のつなぎ言葉が非常に少ない傾向がありました。これもまた、自己に対する過剰な自信を示唆している可能性があります。
- フォーマルな文体: 彼らは全体的に格式ばった、堅苦しい文体を好む傾向がありました。これは、批評家としての地位や権威を重視し、大衆の意見や感情に配慮する意識が低いことの反映かもしれません。
- 分析的かつ形式的なネガティブ批評: 否定的な批評では、単に事実を提示するだけでなく、対象の本質を深く分析しようとする「分析的な文章」と、形式的な文体を組み合わせる傾向が見られました。このような文章は、読者にとって情報処理の負荷が高く、書き手自身も「確証バイアス」に陥りやすい可能性があります。つまり、自分の先入観に合致する情報ばかりを集め、それを裏付けるように分析してしまうことで、誤った結論に導かれるのかもしれません。
- 形容詞が少なく副詞が多い: 「逆神」レビュアーの文章では、形容詞が少なく、副詞が多い傾向が見られました。先行研究では、これらの特徴は外向的な性格と関連しているとされており、彼らが自身の能力を過度に楽観視している可能性を示唆しています。
これらの特徴から導き出される結論は、「逆神」レビュアーたちは、自身の能力を過信し、批評家としての地位や権力をアピールしたい欲求が強いため、映画の成功とはかけ離れた結論に落ち着いてしまう、というものです。簡単に言えば、過剰な自信と先入観にとらわれやすい人ほど、「逆神」になりやすいと言えるでしょう。この傾向は、映画評論の世界だけでなく、ビジネスやその他の予測を伴うあらゆる分野にも当てはまるかもしれません。
「逆神」的批評の具体例
上記の条件を満たした映画レビューがどのようなものか、生成AIに1997年の映画「北京原人」の批評を書かせた例を挙げます。
映画「北京原人」は、1997年に公開された日本・香港合作のSF映画である。第二次世界大戦中に失われたはずの北京原人の頭蓋骨を手に入れた日本政府は、有人シャトルにより宇宙空間において原人のDNA操作を行なう。しかし、そのとき隕石がシャトルに追突し、原人は現代に甦る。
本作は、北京原人と人間との交流を描いた作品である。北京原人は、人間の知能や感情を持ち、人間社会に溶け込んでいく。しかし、その存在は人間社会に大きな衝撃を与え、さまざまな問題を引き起こしていく。
本作の特筆すべき点は、特撮技術の革新性である。当時としては最新鋭のCG技術を駆使して、北京原人の姿をリアルに再現している。また、北京原人の動きや表情も、人間と見分けがつかないほどの精巧さである。
しかし、脚本や演出の面では、残念ながら、期待外れであった。脚本は、SF映画としては、稚拙で、中盤以降は展開が単調になる。また、演出も、特撮シーンは迫力があるものの、人間ドラマの部分は、観客を置いてけぼりにするような、杜撰なものである。
総合的に評価すると、本作は、特撮技術の面では、優れているものの、脚本や演出の面では、論外の作品である。
いかにも「偉そう」なこの文体は、プロの評論家だけでなく、アマチュアのレビューでも頻繁に見られます。もしこのようなタイプの文章を見かけたら、その発言が「逆神」的な傾向を持つ可能性を疑ってみるのも良いかもしれません。
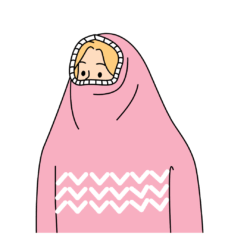


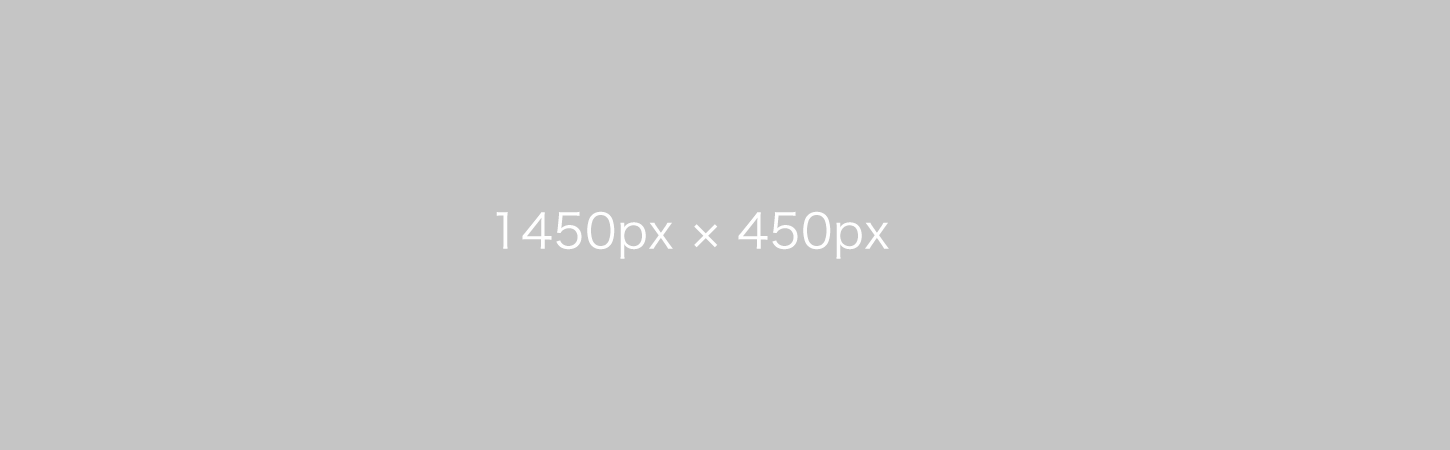
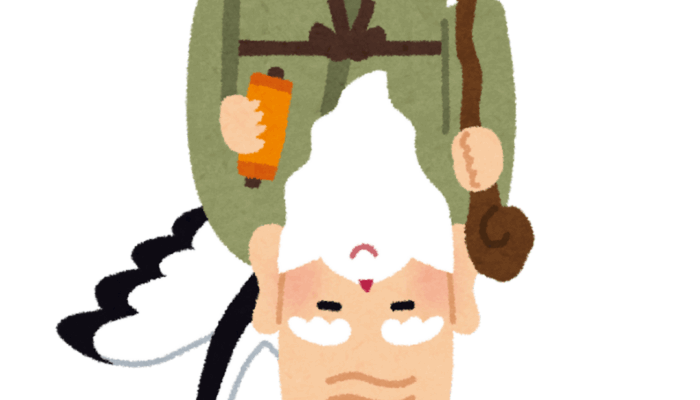
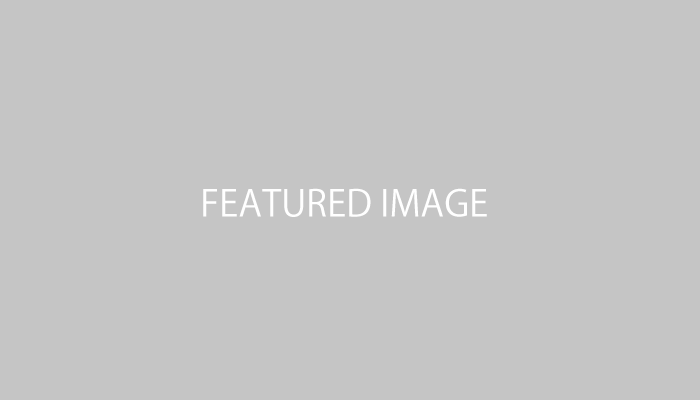

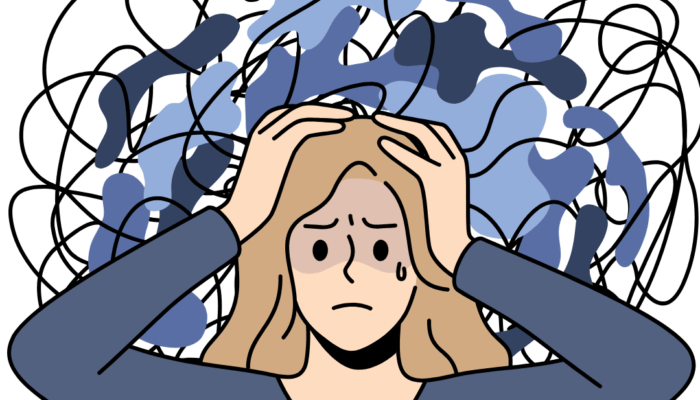



コメント