自己啓発の世界では、多くの人に信じられている定番のメソッドが存在しますが、その中には科学的に根拠が否定されているものも少なくありません。オリバー・バークマンの著書『The Antidote』では、そうした「誤解されがちな4つの自己啓発的主張」が紹介されています。以下に、その内容を要約してご紹介します。
誤解①:怒りは「発散」すべきである
→なぜ誤りなのか?
怒りの感情を発散することでストレスが軽減する、とよく言われますが、実際には逆効果であることが研究で示されています。アイオワ州立大学の実験では、怒りを叫んだり枕を叩いたりして発散すると、むしろ怒りが長引きやすいことが確認されました。
→代替策は?
心理学者ブラッド・ブッシュマンは、怒りを発散するのではなく「紛らわせる」ことを推奨しています。コメディ映画を観る、音楽を聴くなど、気分転換を図るほうが精神的にも良好です。また、感情発散のための激しい運動も逆効果になることがあるため、ヨガやストレッチなどの穏やかな運動が望ましいとされています。
誤解②:落ち込んだらポジティブなイメージを描こう
→なぜ誤りなのか?
「ポジティブシンキング」は自己啓発の基本とされますが、心理学の見解では、ネガティブな感情から無理に目を逸らすほど、逆に意識がネガティブな対象に集中してしまう傾向があることが分かっています。
→代替策は?
信頼できる相手に気持ちを共有する、あるいは心が明るくなるような環境(自然の多い場所、人が集まる場所など)に身を置くことで、自然と気分が回復する可能性が高いとされています。
誤解③:「目標を思い描けば」それが実現する
→なぜ誤りなのか?
「目標を強くイメージすれば成功する」という考え方は広く知られていますが、スポーツ心理学などの研究では、成功のイメージを描くだけでは実際の成果には結びつかないとされています。心理学者シェリー・タイラーは、目標のビジュアライゼーションはむしろ現実的な努力を妨げると指摘しています。
→代替策は?
目標に至るまでの「プロセス」に焦点を当てることが重要です。UCLAの研究では、「目標を達成した自分」ではなく、「勉強している自分」をイメージした学生のほうが、成績が向上する結果となりました。
誤解④:アファメーションで自尊心が高まる
→なぜ誤りなのか?
「毎日ポジティブな言葉を自分にかければ、自尊心が高まる」という説は根強いですが、テキサス大学の研究では、特に元々自尊心の低い人にとって、アファメーションは逆効果になりやすいことが明らかになっています。
→代替策は?
心理学的なアプローチでは、自尊心は他人からの評価によって左右される要素が大きいため、自分を肯定してくれる他者と積極的に関わることが推奨されています。その上で、自らのスキルや人格を磨いていくことが、自尊心を安定的に高める方法とされています。
総括
紹介した4つの主張は、いずれも長年にわたって自己啓発書で繰り返されてきた内容ですが、科学的には否定されているものです。現在もこうした主張を扱う新刊が出版され続けていることからも、情報を鵜呑みにせず、根拠を確認する姿勢が重要であると言えるでしょう。
科学的に否定された「自己啓発本のありがちな誤解」4選
(出典:オリバー・バークマン著『The Antidote』)
自己啓発の世界では、多くの人に信じられている定番のメソッドが存在しますが、その中には科学的に根拠が否定されているものも少なくありません。オリバー・バークマンの著書『The Antidote』では、そうした「誤解されがちな4つの自己啓発的主張」が紹介されています。以下に、その内容を要約してご紹介します。
誤解①:怒りは「発散」すべきである
→なぜ誤りなのか?
怒りの感情を発散することでストレスが軽減する、とよく言われますが、実際には逆効果であることが研究で示されています。アイオワ州立大学の実験では、怒りを叫んだり枕を叩いたりして発散すると、むしろ怒りが長引きやすいことが確認されました。
→代替策は?
心理学者ブラッド・ブッシュマンは、怒りを発散するのではなく「紛らわせる」ことを推奨しています。コメディ映画を観る、音楽を聴くなど、気分転換を図るほうが精神的にも良好です。また、感情発散のための激しい運動も逆効果になることがあるため、ヨガやストレッチなどの穏やかな運動が望ましいとされています。
誤解②:落ち込んだらポジティブなイメージを描こう
→なぜ誤りなのか?
「ポジティブシンキング」は自己啓発の基本とされますが、心理学の見解では、ネガティブな感情から無理に目を逸らすほど、逆に意識がネガティブな対象に集中してしまう傾向があることが分かっています。
→代替策は?
信頼できる相手に気持ちを共有する、あるいは心が明るくなるような環境(自然の多い場所、人が集まる場所など)に身を置くことで、自然と気分が回復する可能性が高いとされています。
誤解③:「目標を思い描けば」それが実現する
→なぜ誤りなのか?
「目標を強くイメージすれば成功する」という考え方は広く知られていますが、スポーツ心理学などの研究では、成功のイメージを描くだけでは実際の成果には結びつかないとされています。心理学者シェリー・タイラーは、目標のビジュアライゼーションはむしろ現実的な努力を妨げると指摘しています。
→代替策は?
目標に至るまでの「プロセス」に焦点を当てることが重要です。UCLAの研究では、「目標を達成した自分」ではなく、「勉強している自分」をイメージした学生のほうが、成績が向上する結果となりました。
誤解④:アファメーションで自尊心が高まる
→なぜ誤りなのか?
「毎日ポジティブな言葉を自分にかければ、自尊心が高まる」という説は根強いですが、テキサス大学の研究では、特に元々自尊心の低い人にとって、アファメーションは逆効果になりやすいことが明らかになっています。
→代替策は?
心理学的なアプローチでは、自尊心は他人からの評価によって左右される要素が大きいため、自分を肯定してくれる他者と積極的に関わることが推奨されています。その上で、自らのスキルや人格を磨いていくことが、自尊心を安定的に高める方法とされています。
総括
紹介した4つの主張は、いずれも長年にわたって自己啓発書で繰り返されてきた内容ですが、科学的には否定されているものです。現在もこうした主張を扱う新刊が出版され続けていることからも、情報を鵜呑みにせず、根拠を確認する姿勢が重要であると言えるでしょう。
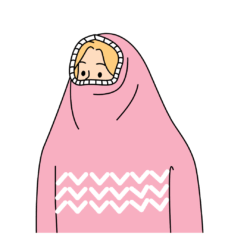


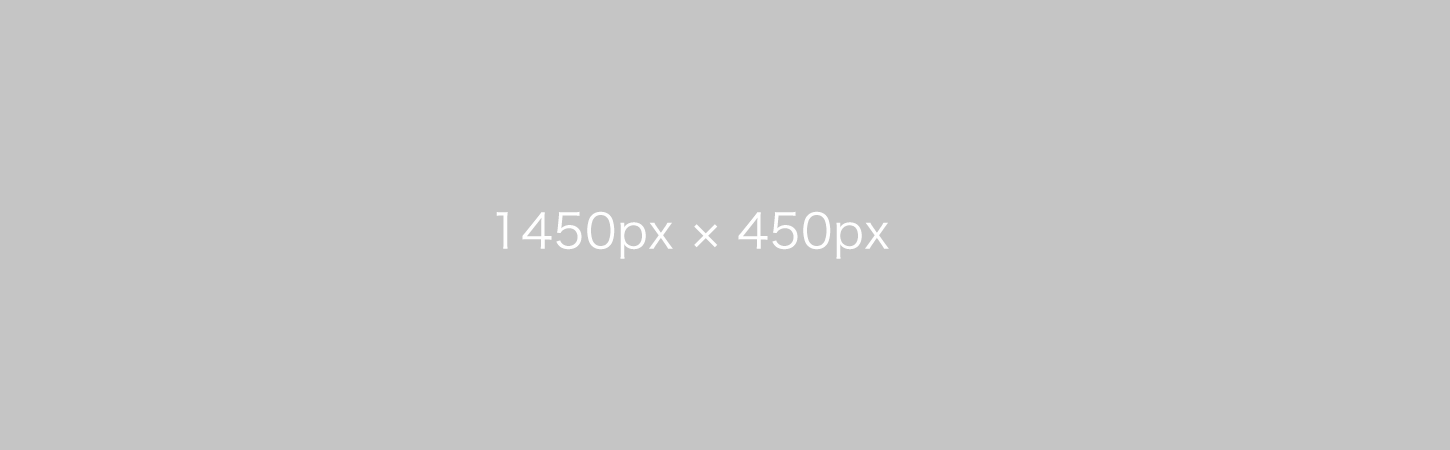
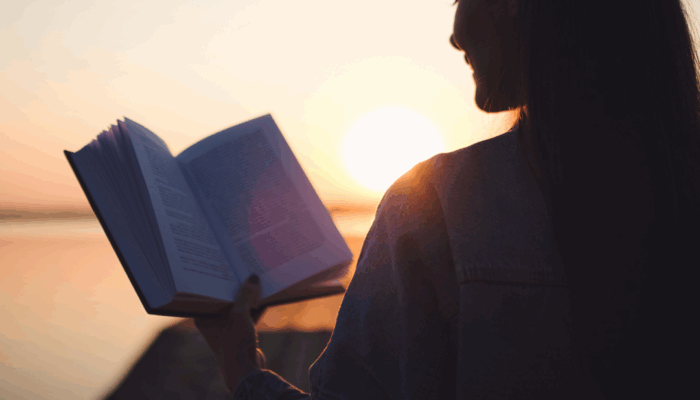






コメント